
Mindful Business
マインドフルビジネス
「マインドフルネス」を漢字で表現すると、「今」(いま)という漢字と「心」(こころ)という漢字を加えた「念」(ねん)という漢字になります。つまり、心の注意力が満たされている状態、心がどこかに拡散していなく、自分のまわりで起きている事象に、すべての事柄に100パーセント集中している状態です。
禅の言葉では「三昧」(さんまい)とも言い換えることができると思います。
これまでの伝統的な仏教などの宗教の中で使われてきた「瞑想」をツールとして切り出し、宗教性を排除したうえで、瞑想を活用することで、今ここに集中し集中力やEQ,対ストレス性などの向上を目指す活動です。現在では、代替医療の現場や教育や経営で使われてきているものです。
マインドフルネスの起源は、禅だとも、原始仏教だとも諸説ありますが、そのオリジンはテーラワーダ仏教におけるサティ(気づき)がベースになっていると説もあります。しかし、正確なところはわかりません。
日本禅のアメリカへの布教の歴史を紐解けば、1893年にシカゴで開催された万国宗教会議において、日本の臨済宗の釈宗演老師がはじめて英語で講演を行いました。その後、釈宗演の弟子鈴木大拙は、1949年から1958年までの二度、アメリカを中心に長期滞在し、西洋社会に禅を広めました。そして、もう一人の弟子である千崎如幻は、1922年からサンフランシスコで「浮遊禅堂」(floating Zendo)をはじめ、日系人とアメリカ人に禅を指導し、日本文化などについて講義を行ったということです。その後太平洋戦争中に突入し、日本仏教の米国での活動は一時弱まります。
戦後、1950年〜60年代に、米国カルフォルニアで、曹洞宗を中心とした幾つかの禅道場ができたことをきっかけに、その後多くのアメリカ人が参禅をおこないました。影響を受けたアメリカ人とカウンターカルチャーなどが結びついた一部の神秘主義のブームが起きました。参禅したアメリカ人の中にはスティーブ・ジョブズ氏も含まれていたということです。
このムーブメントの後、70年〜80年代にかけて次第にカルフォルニアから発信して米国の中に、禅が溶け込んでいきました。その後2000年代に入るとシリコンバレーのITベンチャーの経営者、従業員などが瞑想を行い、ストレスの低減、集中力向上、組織内での人間関係の円滑化などに効果があるということが経験的にわかってきたのです。
最近では、脳波を測定することで、瞑想の集中力強化・ストレスの低減などの効果が科学的に証明されつつあり、米国のマサチューセッツ大学医学部では瞑想の医学的なアプローチからの研究論文が多数出版されていたり、スタンフォード大学ではマインドフルネスの正式な授業があるほどです。
マインドフルネスは当初、GoogleやFacebookまたLinkedinなどのベンチャーでの導入が多かったようですが、現在では、IT業界では老舗のインテル社なども全世界の10万人の社員に対して社員教育の中で瞑想をワークショップの中にとりいれた研修プログラムを導入しています。
マインドフル・ビジネス

欧米では5年ほど前から、このマインドフルネスな状態を一般人や企業に提供することをビジネスにする、トランスフォーマティブ(意識変容)サービスやマインドフル関連ビジネスが立ち上がってきています。日本でも今後、このマインドフルな状態を提供するビジネスがたちあがって行くであろうとおもわれます。
このマインドフル・ビジネスに関する記事がLife Hakerの日本語版で報道されています。
Life Hacker 日本語版記事
『米国で熱く模索される「マインドフルネス・ビジネス」の可能性。有名企業への導入や科学研究も進む』
マインドフル・ビジネスの定義を試みる
これまでは、マインドフル・ビジネスとは、一般人や企業向けの研修などいわいる「教育」のカテゴリーのみと考えられてきましたが、あえて新たな切り口でマインドフル・ビジネスの定義をしなおしてみようと思います。


当社の定義ですが、「マインドフル・ビジネスの定義」を「心の能力向上を目的としたビジネス」と定義してみたいと思います。
人の心の向上の要素として、チームで仕事をするために必要不可欠な他人を思いやる心である「慈愛心」・また家庭成生活だけではなく、仕事にも必要な、今目の前にあることをこなす「集中力」の向上、肉体の感覚から最適な決断を行う「決断力」、現代社会で必要とされているストレスに対する回復力の向上、そして多くの企業で最も必要とされている、イノベーションのために必要な「創造性(力)」の向上の5つとなります。
これまでは、マインドフル・ビジネスとは企業向け研修や、個人向けのカウンセリング、または代替医療などの一部の領域に限定されていました。しかしながら、各業界のなかにこの数年で「マインドフル」の萌芽が芽生えてきており一般にマインドフルビジネスとは関係がないと思われている領域でも、実は「マインドフル」になりつつあります。
そこで、現在のあらゆる産業の中にすでに「マインドフル」な状態を作り出すという目的のビジネスがすでに含まれていると考えてみました。
例えば、今流行の「IoT」産業の中にも、MUSEのように人間の体のバイタル情報をセンサーでキャッチし、それを自らにバイオフィードバックをかけ、自分自身の状態をモニタリングすることで、「マインドフルな状態」を自分で作り出すガジェットなどが登場しつつあるからです。
またAI(人工知能)の業界においても、仮の話ではありまするが、悩みを抱えている人の話をひたすら傾聴することで、人の心を慰める作用をもたらしたり、また禅問答のような対話をすることで、人に気づきを与え、人の心の成長をたすけるようなAIが登場すれば、それは十分にマインドフルビジネスのカテゴリーに入ると思われます。
つまり、それぞれの産業の中に「マインドフルな状態を目指す」製品やサービスなどが、すでにもう含まれており、それを切り出して合算すれば、大体の「マインドフル・ビジネス」世界市場規模になるのでは?と、ざっくりっと考えたわけです。
マインドフル・エコノミーにおける顧客像と価値観
マインドフル・エコノミーのなかで生み出されるビジネスの対象となる消費者の属性は、米国、ヨーロッパの一部、日本、など限られた先進国の中の富裕層になるであろうと想定しています。先進国で資本主義が十分に行き渡り、モノやサービスがすでに身の回りにお溢れているような国の中でも富裕層のカテゴリーにあたる人々であり、そのような富裕層においては、生活基盤は安定しており、さらに家や車など生活に必要な基盤はすでに持ち合わせていると考えています。
そのような、マインドフル・ビジネスが多く提供される市場である、マインドフル・エコノミーの中で、顧客が価値と感じる価値観を4つに分けて以下のように定義してみました。
1. Functionality (機能)
提供される製品やサービスの基本的な機能のことです。たとえば、洗濯機であれば最低限の洗濯ができることであり、冷蔵庫であれば冷蔵庫内にある食品が設定した温度で冷やされることです。例えば日本において、製品・サービスにおける「昭和」の価値観では、これまでの商品において基本的な機能自体が製品やサービスに不足していたことから、重要視されていました。しかし、昭和から平成の時代の流れと共に、その機能の価値は相対的に半分となり、変化していきました。昭和から平成にと機能とそれ以外の価値を比較すると、感覚的にはちょうど半分・半分という段階にあると定義しています。
2. Design (デザイン)
デザインは一般消費者が商品、サービスを選ぶ際の最も重要な要素の一つであり続けました、元号で言えば昭和の末期になり、ときには機能性を凌駕するほど重要な商品・サービスの重要な価値となりました。ちょうど平成が終わる頃には、「デザイン」は機能性を覗いては最も大きな商品に対する大きな付加価値となりました。しかし、一方でデザイン優先の価値観は、商品のライフサイクルをはやめ、時にはすべての商品・サービスがトレンドに応じて変化するために、外観上非常に似通ったものにさせてしまうなどの弊害もうみだしたのです。
3. Experience (体験)
マインドフルエコノミーの中で対象となる顧客にとっての製品価値にふくまれる「体験」の価値は非常に大きなものになっていると考えています。他の先進国と同様に、日本においての体験価値は平成に入り大きくなってきており、平成の最後にはこの体験価値が一般消費者向けには大きな割合を占めるようになってきています。
4. Social / Loaclity (社会性)
マインドフル・エコノミーの対象とする顧客は、これまでの資本経済の中で多くの製品やサービスを体験した、いわば十分に資本守護の恩恵をうけ、さまざまな製品・サービスでトレーニングされた顧客です。そのようなトレーニングされた顧客にとって、これまでの資本主義の先にあるもの、それが商業活動として提供されるのがマインドフル・ビジネスであり、そのような顧客は自分が購入する製品やサービスが地域社会にどのような貢献があり、またどの環境に対してどの程度の貢献ができるのかということが重要になってきます。
5. Self-transformation (自己変容)
この概念は、これまでの1で述べたExperience (経験)と混同されやすいのですが、マーケティングの世界で言われる「Experience (体験)」とは異なった概念です。マーケティングのなかで定義されるExperience(体験)は、時間が経つに連れて、体験からくる記憶や、意識の変容などは失われていきますが、Self-transformationは「不可逆なも」のであると定義しています。つまり、一度Self-transformation experience(自己変容経験)を体験したユーザーは、個人の中の価値観が大きく変化し、その意識の状態は体験前とことなり不可逆的に変容します。マインドフル・エコノミーの中で提供される製品やサービスの最終的な目的が、Self-transformation(自己変容)を目的としている商品であると想定しています。

時代とともに変化する消費者の商品・サービスに関する商品価値

マインドフルビジネスの対象となる消費者の製品・サービスに対しての価値観の変化を、日本人が感覚的にわかりやすいわかりやすい元号で表してみました。
昭和の価値観:
一般消費者向けの市場において、製品が必要とされる基本的な機能を果たすこと必要な時代でした。なのでまずは機能性を重視したのが、昭和の時代の価値観であったということが言えます。しかし、昭和から平成へ元号が移行するころになると、一般消費者は次第に機能性以外の価値を求めるようになってきました。そ大きなところがデザイン性でした。
平成の価値観:
平成時代の価値観では、一般消費者はしだいに商品やサービスの機能以外の価値に重点を置くようになってきました。いわいる付加価値と言われるものですが、平成の末期の現在では、機能性と機能性以外の部分の価値観(デザイン・体験・社会性)がちょうど50パーセントづつというところまできているのではないでしょうか。
新元号の価値観:
日本は今年、あらたな元号になります。日本が新しい時代に入っていくのです。モノやサービスが隅々まで行き渡った日本という先進国、その中で先端をいく顧客層は何を重要と感じるのでしょうか?
この新しい時代に顧客が重要視する商品やサービスの基本的な機能はあって当たり前、さらにデザイン・体験・社会性に価値の重点をおくようになっていくでしょう。そして、その先にある顧客の価値観が、Self-transformatoin (自己変容)を置と考えています。それが現在のマインドフルネスの流行につながっており、自己変容を引き起こさせてくれるような要素がある製品、サービスに価値を見出す顧客がふえていくと考えています。
マインドフルビジネスの市場規模

その市場規模はどれくらいあるのか?
はたして、マインドフルネス市場の大きさはどの程度なのだろうか?という疑問から、海外の調査レポートなど散々に検索しても、それらしき数字は出てきませんでした。
海外のWEBを探ると、雑誌フォーチュンのこのこのような記事や、NYCの関係者がまとめたMBSR(Mindfulness-Based Stress Reduction Program)の市場規模などを見つけることができました。そもそも、未だマインドフルネス市場は立ち上がっていないのかもしれませんし、立ち上がっていない市場を予想するのは非常に難しいのだと思われます。
(2018年12月5日追記:)2018年11月、サンフランシスコにて”TRANSTECH”という小規模なカンファレンスが開催されました、そのカンファレンスで提示された、トランスフォームテクノロジー(マインドフル・ビジネスのカテゴリーと重なる)の市場規模は、300兆円であると試算されています。我々の試算である211兆円を上回る規模ですが、我々が予想していた数百億円規模になるということは、我々と同じであると認識しています。まずは、マインドフルネス・ビジネスとしてどのような市場カテゴリーがあるのかということを以下にまとめてみました。
1. IoT&ものづくり
IoTとモノづくりの市場におけるマインドフルネス市場の予想を考えてみましょう。マインドフルネスのブームとともに、自宅でも坐禅や瞑想を行う方が増えてきています。
自宅の近くに禅寺があるような恵まれた方は、定期的にお寺に通い指導をしていただけば良いのだとおもいますが、そうではないメディテーターのために、IoTを用いて瞑想をアシストするような必要性が出てくるのだとおもいます。
そこで、IoT市場でも、先の取り上げたMUSEのようなマインドフルネス瞑想をアシストするような製品が登場すると思われます。マインドフルに特化したセンサーのようなバイタルセンサーなども含まれると考えれられる。この数字はあくまでも既存の市場データを参考にして、非常にざっくり算出してみました。
追記:2019年2月7日の米国Venture Beatの記事では、マインドフルビジネス初のユニコーン企業(※ユニコーンとは市場価値が1000億円以上とされる企業のこと)として、 米国のマインドフルApp開発企業のCalmを報道しています。シリーズAとして90億円台の調達をおこない、企業価値としては1100億円であると報道されています。

マインドフルネス関連の企業として、企業価値が初めて1000億円を超え、ユニコーン企業企業になった��マインドフルApp開発会社「Calm」をつたえる報道記事に関してはこちらを御覧ください。(出所:Venture Beast)
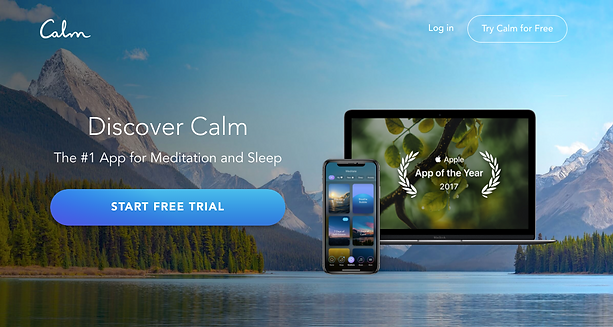
マインドフルアプリ開発会社Calmのホームページ

2.自動車自動運転・AI・ロボット分野
MuseのようなIoTデバイスだけではなく、将来は自動車などのモビリティ分野でも、車の運転ハンドルから心拍数や体温、呼吸数などの人体データー取得し、運転者の心理状態を予測して、運転者の心理状態を運転するに最適なものに誘導するような仕組みが考えられます。
例えば、運転者の精神状態が、興奮状態にあれば、落ち着くための音楽や、匂いを車内に提供し、最適な心理状態にして、事故率を下げたりするような装置のカテゴリーも、実は人の心の能力(集中力)を高めたりというアプローチになるので、マインドフル・ビジネスに入っていくのではないでしょうか。
同じように、バイタル・センサーにより、生体情報を読み取り、そこからクラウド上にデータを飛ばして計算を行うことで、心理状態を推察できるようになると、人の心がわかる各種デバイスが出来上がるようになります。
ところで、Appleの最新IOS10でもApple Watchとして連携し、生体データを取得していくデータロガーの中のヘルスデータのカテゴリーの中に、マインドフルネスが追加されたということで、今後、マインドフルネスのニーズがいかに高まっているのかがわかり、このような流れは加速していくことでしょう。
また、その他の事例として、最近、川崎重工が発表した「人格を持つ“AIバイク”」コンセプトの中でも、 ”ソフトバンクグループのcocoro SBが開発した「感情エンジン・自然言語対話システム」を活用。ライダーの話す言葉から意思や感情をAIが理解し、言語を使って意思疎通する。ソフトバンクグループのcocoro SBが開発した「感情エンジン・自然言語対話システム」を活用。ライダーの話す言葉から意思や感情をAIが理解し、言語を使って意思疎通する。” とされています。
このコンセプトはユーザーの感情からバイクのセッテイングなどを少しづく変えていくということでありますが、将来的にはユーザー側に音や振動、対話などを通じてユーザーの心を落ち着け、運転に最適な心理状態へ整えるということもできると思います。
そのように、ユーザーの声、体温・心拍などの生体情報から人間の感情を読み取る「感情エンジン」は、これから様々なデバイスやロボットに組み込まれる非常に重要な技術になると思われます。この感情エンジンを組み込んだOSは、将来的にAI・ロボット技術の根幹技術になるのかもしれません。

3.教育
教育分野は、もっともわかりやすいマインドフルネスビジネス分野です。マインドフルネスを教育プログラムの中に導入した結果、人の心の能力である「集中力」、レジリエンス(対ストレス性)、「創造性」などが向上するということが言われています。
先進国などでも、貧困地区の公立学校における児童の集中力欠如により学級崩壊が深刻な問題になっているということですが、そのような教育環境の中でマインドフルネスを導入することは、児童の精神の安定と「集中力」の向上、その結果としての学力の向上が見られるという研究なども、ヨーロツパのポジティブ・サイコロジーでの学会などでも発表されています。
とくに瞑想を中心軸においたマインドネスプログラムの導入は、とくに物理的なものを購入する必要はなく、導入にそれほどコストがかからないことから、安価な投資て公共教育のレベルを押し上げる有効な手段として考えられているようです。
公共的な教育機関においての児童の学力レベルがあがれば、15〜20年後には、卒業した児童が生産人口となり、生産人口である地域住民の収入レベルがあがり、結果として住民税の向上を見込めるとも考えているようです。
また、この分野では義務教育だけでははく、社会人教育のなかでもマインドフルネスは期待されています。
例えば、企業研修などのカテゴリーでは、GoogleやSAPなどですでに導入されているリーダーシップ教育「Search Inside Yourself」などがあります。ストレスに対するレジリエンス(対ストレス性能力)、創造性の向上などの効果を期待されており、今後発展の可能性が非常に大きくなることが期待されています。
義務教育での事例では、英国議会の有志メンバーによってまとめられたMindful Nation UKというレポートの中で英国のマインドフルネスの導入の可能性に関してレポートしており、その中では、公共教育の中だけではなく、刑務所なかでのマインドフルネス導入が提唱されています。英国では英国議会の中でマインドフルネスを支援する超党派の議員連合があるようで、英国議会において、議員による3分間の瞑想も実施されたということです。

英国議会有志議員らによる“MINDFUL NATION UK”レポート

4.ヘルスケア
マインドフルネスはストレスに対する、レジリエンス(対ストレス性能力)を向上させ、免疫力を上げることが米国マサチューセッツ大学の医学部などが中心として行ってきた研究でわかっています。
日本の大手企業においても、最近は特にメンタル的な問題顔抱えている社員が多い中で、マインドフルネスがそれらの社員の精神的な問題の改善を促すものとして期待して良いでしょう。この分野では、B2Cだけではなく、B2Bの市場のニーズが非常に高いことから、欧米を中心として企業向けのマインドフルネス・ワークショップなどが盛んに導入されています。
また、米国の一部の病院では、激しい痛みを抱えている患者のためにマインドフルネスが導入され、成果を出していることことから、先進国を中心に医療分野でのマインドフルネスが進むでしょう。
また、人工知能の発達によって、家庭の中でも音声認識技術を活用し、インターネットでつながったクラウド上で行われて、フィードバックが戻るようなAIが導入されていくでしょう。さまざまなセンサーを用いて人の心理状態を把握することで、人の心を落ち着かせるようなAIコーチングやAIメンタリングなどの市場も広がることが想定されます。
これまでの観光業は、単純に風光明媚な場所などの観光地めぐることがメインでした。これからの観光は、ヒーリングを目的にいわいるパワースポットを巡ったり、そのようなな場で「リトリート」といわれる
ヨガやマインドフル瞑想などを組み込んだ体験型のツアーが増えていくでしょう。
「リトリート」の中では寺社仏閣や自然の中でもスピリチュアルな場所などで、瞑想指導者により瞑想指導を受けたり、自然の森に入り、その森の中の沈黙の中で、自分自身を見つめなおすことなど、これまでの観光地へいって、お見上げものを購入するような観光ではなく、人の心の能力を上げるため、「リトリートツアー」に参加したり、リトリート参加者のための、注目ヨガスタジオや瞑想する施設をそなえたホテルや旅館なども必要になってくるのだと思います。

5. アート
瞑想や禅を行い、瞑想中に出てきたイメージなどに触発され、生み出された作品、あるいは音楽なども、今後ますます盛んになって行くでしょう。
実際に、国内外多くのクリエーターが、禅や瞑想にインスピレーション禅の道場に通っていましたし、今後も其の流れが加速するでしょう。芸術家や小説家などのクリエイティブ人材のなかでも禅や瞑想を実践する人々が増えていくことでしょう。
6.コンテンツ産業
このカテゴリは娯楽とも重なるのですが、音楽・映画・アニメ・小説・漫画など、人に「気づきをあたえる」ような内容のコンテンツが増えて行く事になります。
すでに書籍の分野では「自己啓発系」と呼ばれているカテゴリーの書籍が、国内のみらず海外でも確立されています。場合によってはその関連の書籍の売上は頻繁にベストセラーに入ることもあるような流れになってきています。
また映画の分野でも、おなじく「自己啓発系」「気付き系」とも呼ばれるカテゴリーの作品はフィクションだけではなくドキュメンタリーなどにも広がっていくでしょう。

7. 金融
「金融」と「マインドフルネス」というと、異なるイメージがするかもしれませんが、「鎌倉投信」さんや、「さわかみ投信」などでやられている、人の顔が見える形の長期的ファンドであったり、場合によっては、プロジェクト共感型のクラウドファンディングや、P2Pのローンなどのソーシャルレンディング、あるいはマイクロファイナンスなどのカテゴリーも、貸し手と借り手とともに、マインドフルな思考ににもとづいて��融資・投資をおこなっていく必要がでてくるので、マインドフル・ビジネスの一部として試算に組み込みました。

8. 観光
これまでの観光業は、単純に風光明媚な場所などの観光地めぐることがメインでした。これからの観光は、ヒーリングを目的にいわいるパワースポットを巡ったり、そのようなな場で「リトリート」といわれるヨガやマインドフル瞑想などを組み込んだ体験型のツアーが増えていくでしょう。
「リトリート」の中では寺社仏閣や自然の中でもスピリチュアルな場所などで、瞑想指導者により瞑想指導を受けたり、自然の森に入り、その森の中の沈黙の中で、自分自身を見つめなおすことなど、これまでの観光地へいって、おみあげものを購入するような観光ではなく、人の心の能力を上げるため、「リトリートツアー」に参加したり、リトリート参加者のための、ヨガスタジオや瞑想する施設をそなえたホテルや旅館なども必要になってくるのだと思います。
実際、2919年に入りオンライン旅行会社のアゴダで日本、オーストラリア、中国、イスラエル、サウジアアビア、フィリピン、アラブ諸国連邦の7カ国で実施した調査によると、2019年旅先で体験したいことに関する調査で、すべての年齢層において、セルフケア・リトリートが2位にランクインしています。まさに、マインドフル・ツーリズムの大きな流れが来ていると思われます。記事の詳細はこちらをご覧ください。

9. 娯楽(ゲーム・アミューズメント・アウトドア・レジャー・スポーツ)
オンライン・ゲーム、ゲームAPP、アミューズメント・パーク、スポーツの分野などでも、人の心の能力向上や気付きをあたえるものが増えるでしょう。
大きな変化は、アウトドアやスポーツ分野で、ヨガなどにマインドフルネス瞑想を組み合わせたものや、「トレイルラン」X「マインドフルネス」など、さまざまな既存のスポーツに「マインドフルネス瞑想」を組み合わせるタイプのスポーツが増えていくでしょう。
「既存のスポーツ」x「マインドフル」が増えると、たとえば野外での瞑想をするのに適したウェアや、ヨガマット、あるいは坐布のようなギアが開発される必要があります。
また、新たに生み出されたマインドフルなスポーツを教える教室やワークショップなども生み出されることになります。
以下の様なマインドフルネス X ランニングを掛けあわせた、マインドフルランニングというような新たなスポーツカテゴリーがどんどん生み出されるイメージがです。
今後はスポーツは、単純に肉体のトレーニングだけではなく、人の意識レベルの向上を目的とし、脳や精神も鍛える新しいカテゴリーの「マインドフルネス・スポーツ」が登場していくことでしょう。

米国セドナでトレイルの後、瞑想を楽しむ
2025年マインドフル・ビジネス市場はブラジルのGDPと同じ
マインドフルビジネスのマーケット:211.8兆円
-
IoT&ものづくり:9兆円(幸福度を測定する機器製造)
-
自動車・AI・ロボット:34.4兆円(自動運転支援、AI、ロボット)
-
教育:40兆円(幸福学、zenschool、lifeschool等)
-
ヘルスケア:52兆円(予防医学、メンタルケア等)
-
アート:6.7兆円
-
コンテンツ産業:1.2兆円
-
金融:1.4兆円(鎌倉投信、CF、ソーシャルレンディング等)
-
観光:14.6兆円
-
娯楽関連:52.7兆円(スポーツ、アウトドア、ゲーム、レジャー)
本数値の算出方法は、現在手に入る既存の産業分野市場規模の数値から、どの程度が「マインドフル・ビジネス」に移行しそうかを、ざっくり予測してかけていくという、非常に「乱暴な」算出方法にしております。
この数字だけ見てしまうと、「すわ、明日から、マインドフルネス・ビジネスの時代が来る!」と勘違いしてしまいそうですが、
実際にはマインドフルビジネスというものが、全く新たに立ち上がるというイメージではなく、すでに既存に存在している市場の中で、マインドフルネス的な要素を含んだ市場規模が9年間をかけて徐々に増えていくイメージです。
本数字は、ずいぶん大風呂敷な数字だと思われる方も多いとおもいますが、これが今わたくしどもが感じているイメージを数字にしてみたものです。
当社はそのようなマインドフル・ビジネスを生み出すための起業塾として中小企業、ベンチャー、大企業向のイベベーション担当者向けに我々が開発した、マインドフルビジネス・プログラム「zenschool(ゼンスクール)」を運営しており、すでに22期を迎えました。卒業生の方々は、非常にさまざまな製品やサービスが生み出しており、人間の心には無限の能力があると日々感じております。よろしければ体験いただくためのワークショップをおこなっておりますので、ご参加検討くださいませ。
マインドフル・ビジネス提唱者

代表取締役: 三木康司
1968.5.28生まれ
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 後期博士課程単位取得退学
明治学院大学卒業後、富士通株式会社に入社、海外営業部に配属される。
その後、慶應義塾大学、藤沢キャンパス(SFC)にてインターネットを活用した経営 戦略を研究するため、自費留学。同校にて政策・メディア修士号を取得後、博士課程へ進学、リサーチを兼ねて中小製造業支援ベンチャーに 入社するが、業務多忙のため博士課程は学位を取得せず単位取得後退学。同社は国内最大規模の製造業ポータルサイトに成長、IT担当役員を務めた後、事業悪化に伴いリストラされる。
リストラのショックで軽度のうつ状態に陥るが、自身の心のケアのため毎朝の坐禅を自宅で開始、その後、坐禅により心の安定と、様々な事業アイデアが生み出されることを自ら体感し、それを中小企業の自社製品開発、新規事業に応用する中小企業のためのzenschool(ゼンスクール)を構想。2009年だれもがメーカーになれる、「マイクロモノづくり」の概念を普及するために、株式会社enmono を独立、起業。2018年6月、いままでの実績をまとめた「True Innovation」を出版。
2017年、国内初の禅とマインドフルネスの国際カンファレンス「Zen2.0」を北鎌倉の建長寺にて主催者として成功させる。2018年も引き続き開催、世界の禅やマインドフルネスの実践者を呼びバイリンガルでの国際会議を成功させ、国内だけではなく海外からも注目される。「マインドフル・ビジネス」、「マインドフル・エコノミー」の提唱者。
これまでの当社活動についての、マスメディアの報道実績を見る。
マインドフル・ビジネスについて解説した書籍

